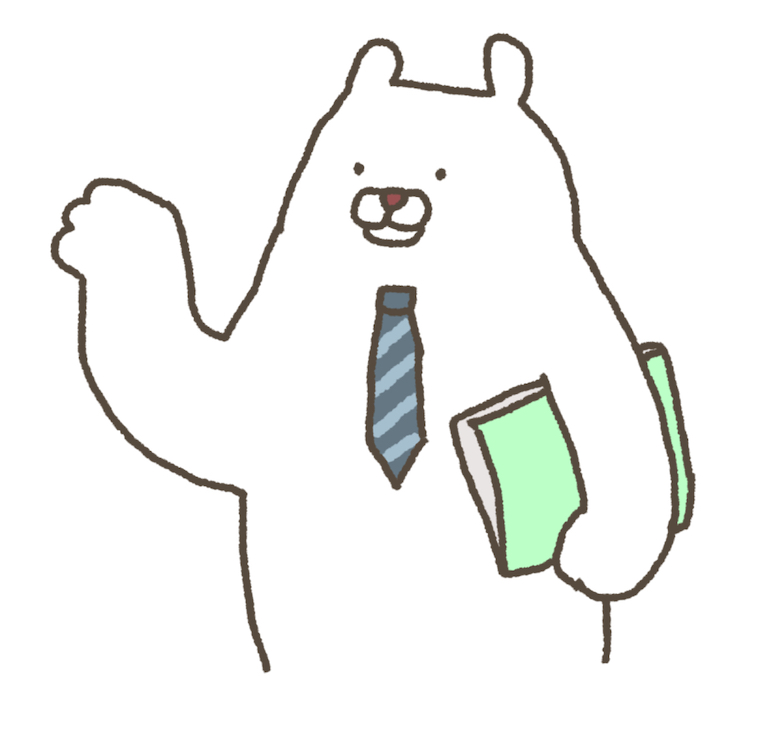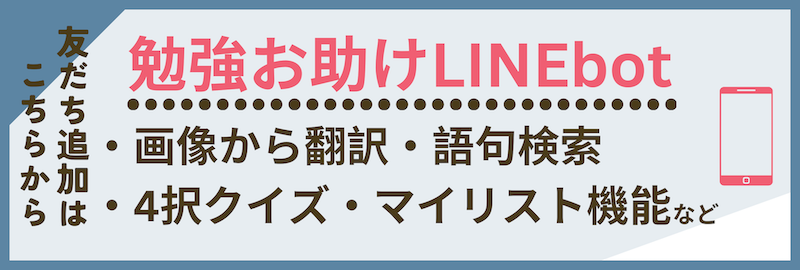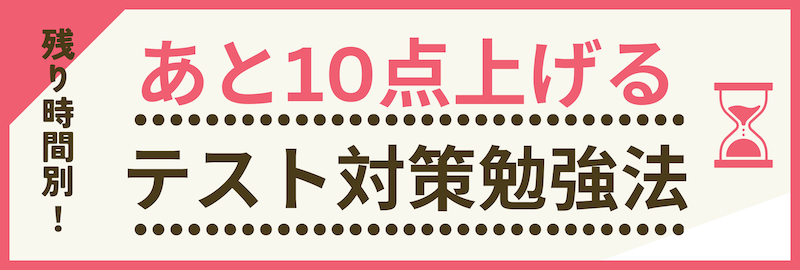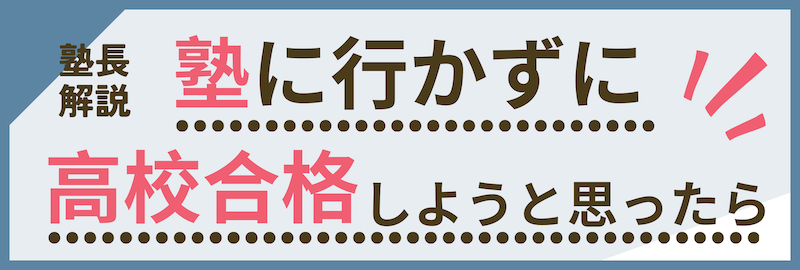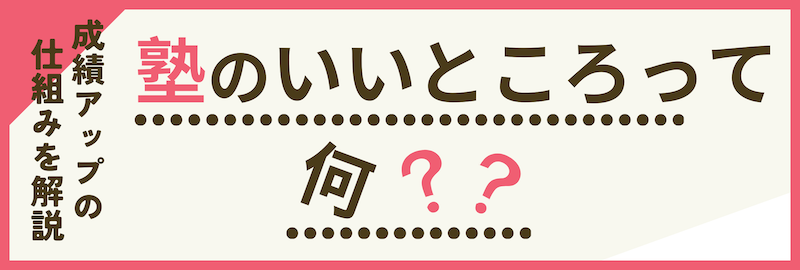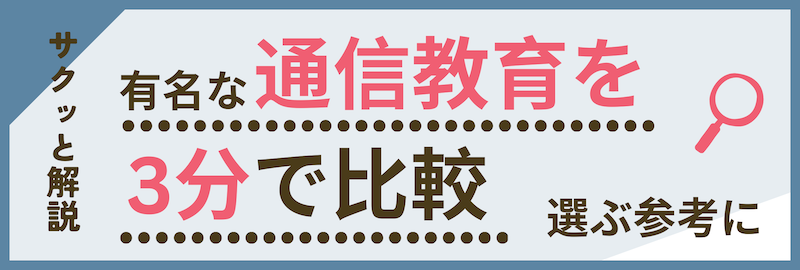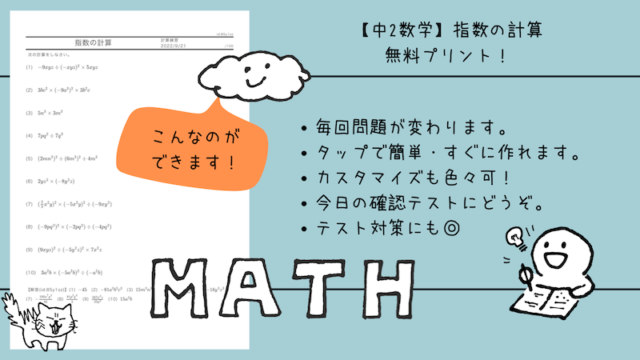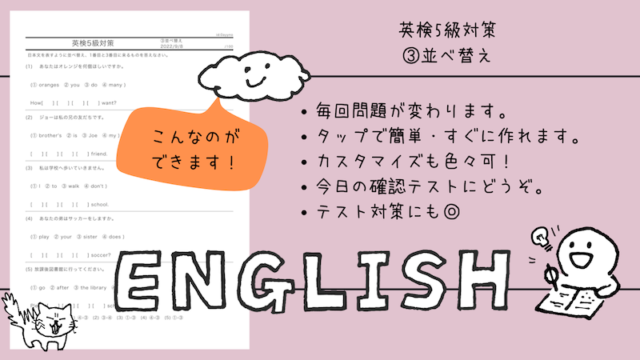今回は中学生が音楽で鑑賞する『ブルタバ(モルダウ)』についてまとめました!
ということでモルダウ(ブルタバ)の鑑賞課題はここでできます!
このブルタバわたしが学習した頃は『モルダウ』って呼ばれていたんですよね。
ただこの曲自体が「オーストリア帝国の支配からの解放の思い」が込められたものとされます。
そして『モルダウ』というのは川の名前で、国際的な呼び名かもしれません。
しかし、オーストリア帝国による支配も感じさせるものです。
解放の思いを込めた曲の名前が、支配を感じさせるものでは、確かにおかしいですよね。
つまりどういうことかも含め、色々解説していきますので、ぜひ見ていって下さい。
タターンタ、ターンタ、タンータタ、ターン、ターン、ターン…すごい頭に残るんですよね。あ、ちゃんと音源もあるので聞けますよ
contents
ブルタバ(モルダウ)とは

- 連作交響詩『我が祖国』の第2曲
- 作曲者:ベドルジハ・スメタナ
- ブルタバはチェコ共和国最長の川の名前
- チェコ語ではブルタバ、ドイツ語ではモルダウ
●連作交響詩とは
- 連作→いくつかの作品で構成される
- 交響詩→オーケストラで演奏される、ストーリーのある音楽
連作交響詩『我が祖国』は
- ビシェフラト
- ブルタバ(モルダウ)
- シャルカ
- ボヘミアの森と草原から
- ターボル
- ブラニーク
の6曲から構成される
ベドルジハ・スメタナについて
 Bedrich Smetana - ベドルジハ・スメタナ - Wikipedia
Bedrich Smetana - ベドルジハ・スメタナ - Wikipedia
- 名前:ベドルジハ・スメタナ(Bedřich Smetana)
- 生まれ:1824年3月2日
- 〜没:〜1884年5月12日(60歳)
- 活躍した場所:現在のチェコ、スウェーデン
- ジャンル:チェコ国民楽派、ロマン派
- 代表作:『我が祖国』『売られた花嫁』『弦楽四重奏曲第1番 「わが生涯より」』など
- チェコのボヘミアに生まれ、幼少の頃からヴァイオリンとピアノを習う
- 6歳でピアノの公演、8歳で作曲をした
- 1839年の15歳頃、プラハ(チェコの首都)に進学
- 学校に馴染めず学校には行かなくなった→音楽活動に没頭
- 一時は連れ戻されるが1843年に再びプラハに
- 1848年、音楽家として活動する中、革命運動(オーストリア皇帝からの解放)の手助けも
- 1850年、オーストリア皇帝フェルディナント1世の宮廷ピアニストになる(←→革命運動の逆?)
- 1846年、「プラハは私を認めようとしない。だから私は離れる」と言いスウェーデンのヨーテボリに引っ越す
- 1862年頃、再びプラハへ→指揮者として活躍したい!(民族主義的にもいい方向に向かっていた)
- →大活躍をしてチェコの劇場(仮劇場)の首席指揮者に!
- 戦争などの不安定な国際情勢や、音楽界内での権力争いの中で聴力を失う(スメタナ50歳頃)
- 1874年〜1879年、作曲を続け『我が祖国』を作曲
- →楽曲が大きな人気を得てチェコ国民楽派を代表する音楽家になる
- 1884年5月12日、60年の人生を終える
現在、スメタナの命日である5月12日には毎年「プラハの春音楽祭」が開催される。
プラハ春音楽祭は著名な音楽家やオーケストラが招かれる国際音楽祭で、
- オープニング→スメタナの『我が祖国』
- 場所→プラハ市民会館の中の「スメタナ・ホール」など
と、スメタナを称える音楽祭になっている。
(2020年は新型コロナの影響でオンライン開催となりました。)
●国民楽派
自分の民族独自の歴史や文化を大切にし、楽曲に取り入れた音楽家のスタイル
●ロマン派
ロマン派は古典派に対する表現で
- 形式の自由さ
- 庶民のための楽曲
を特徴とする音楽家のスタイル
※古典派→貴族のための音楽、ベートーヴェン
詳しくはこちらも!
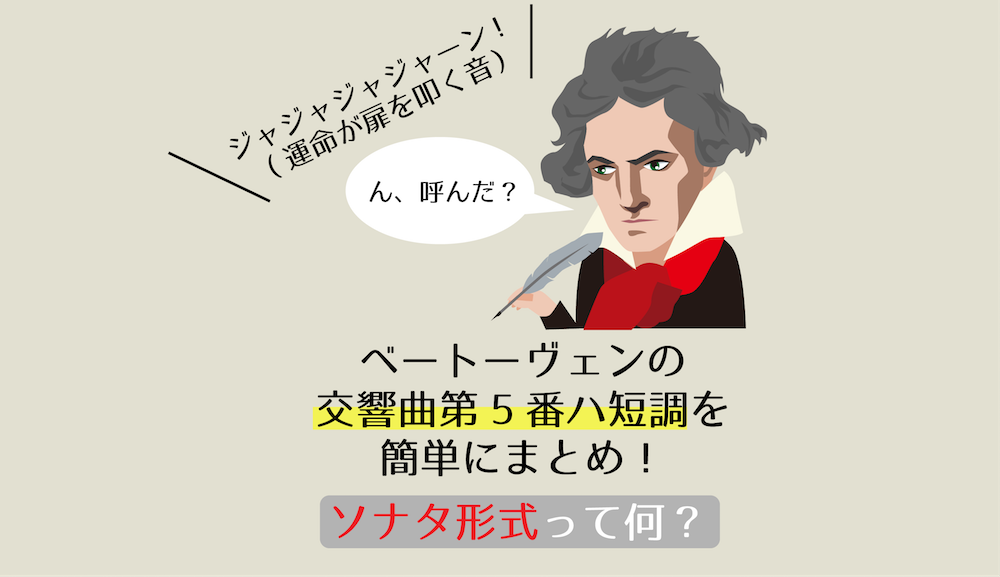
プラハとチェコの歴史的背景
19世紀後半、スメタナが活躍した頃のプラハ
オーストリア・ハンガリー帝国の一つの都市に過ぎなかった
(現在はチェコ共和国の首都)
プラハの歴史

かつては神聖ローマ帝国の首都
- 黄金のプラハ
- 15〜16世紀はヨーロッパ文化の中心
と、とても栄えていた。
*神聖ローマ帝国(962〜1809)はドイツ・イタリアを中心にした帝国
↓
 Defenestration-prague-1618 - 三十年戦争 - Wikipedia
Defenestration-prague-1618 - 三十年戦争 - Wikipedia
三十年戦争(1618〜1648)と呼ばれる宗教戦争を経て、プラハから宮殿がウィーン(オーストリア)に移される
→プラハは急激にさびれ、チェコ語の禁止など、文化的・宗教的に押さえつけられる
※画像は三十年戦争のきっかけと言われる「プラハ窓外放出事件」を表したもの
(何が事件かって、色々あって怒った民衆が、王の使者をプラハ城から投げ落としたんです…)
↓
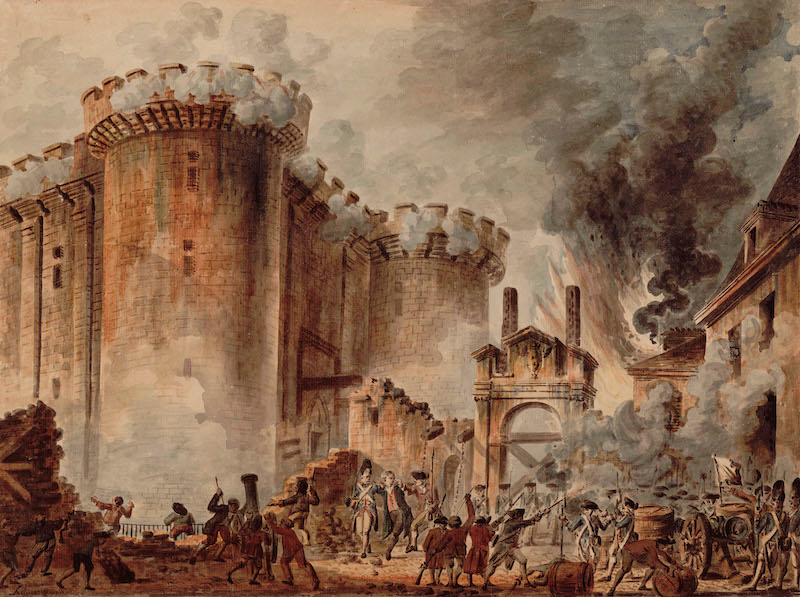 Prise de la Bastille - フランス革命 - Wikipedia
Prise de la Bastille - フランス革命 - Wikipedia
1879年のフランス革命をきっかけに、プラハでも民族主義運動が活発に!
1848年の革命運動にはスメタナも少し関わる→しかしすぐに鎮圧
※画像はフランス革命の始まりの、「バスティーユ牢獄の襲撃」です。
(3年生は覚えておいて!)
↓
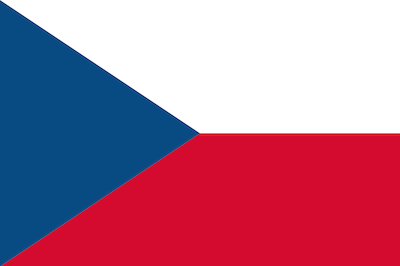
1918年、チェコ・スロバキアとしてオーストリア・ハンガリー帝国から独立
1993年にチェコ共和国として独立した
※画像はチェコ共和国の国旗です。
現在のプラハ

- 「音楽の都ウィーン(オーストリア)」にならび「音楽の街(City of Music)」と呼ばれる
- →ドヴォルザーク、モーツァルト、チャイコフスキー、ハイドンらも訪れた(音楽会のレジェンドたち)
- 街中のいたるところで音楽演奏がされている
- 中世ヨーロッパの街並みが残る「世界で夫も美しい街」の一つとされている(映画のロケ地『のだめカンタービレ』も)
現在は「音楽の街」と呼ばれるまでになりましたが、スメタナの頃はオーストリア帝国に支配され、チェコ語などの文化も禁止されていました。その支配からの解放と民族の文化の復活をを求めて作曲したのが『我が祖国』だということなんですね。
『我が祖国』第2曲ブルタバ(モルダウ)について

- ホ短調(悲しみや暗いイメージ、他には『新世界』ドヴォルザーク、『硝子の少年』Kinki Kidsなど)
- 長さは12〜13分
- ブルタバの源流〜プラハ〜エルベ川への合流を表現
- 7つの場面からなる
- 当時はチェコ語は禁止、ドイツ語が強制されていたため『モルダウ』とされた
ブルタバ(モルダウ)の7つの場面
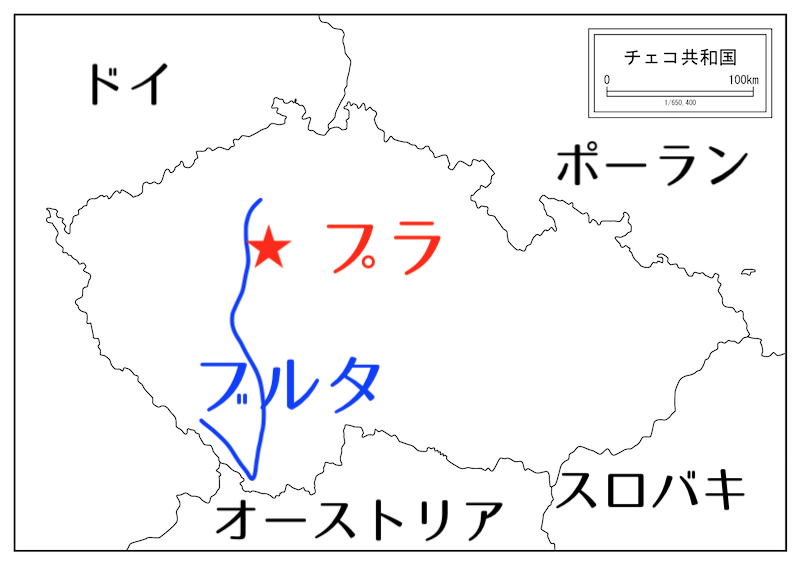
- [A]ブルタバの2つの源流
- [B]森の狩猟
- [C]農民の結婚式
- [D]月の光、水の精の踊り
- [E]聖ヨハネの急流
- [F]幅広く流れるブルタバ
- [G]ビシェフラトの動機

楽器:フルート、クラリネット
- 水源から湧き出す小さな水の流れを表現
- 小さな音で演奏される
- その後ヴァイオリンとオーボエが合流
- 2つの流れを緩やかに表現
- ブルタバの有名な旋律が演奏される

楽器:ホルン
- 力強く響き渡る
- 川がどんどん大きくなっていく様子を表す

楽器:ヴァイオリン、クラリネット
- チェコの民族舞踊ポルカが演奏される
- 農民たちが結婚式のお祝いで楽しそう
- 水の流れの雰囲気はなくなっている
●ポルカとは
ポルカはボヘミアの民族舞踊で、2/4拍子の早いリズムで演奏されるのが特徴です。
また、回転舞踊曲とも呼ばれ、スキップしながら回転するアレですね!(動画参照↑)
ボヘミアはブルタバ側流域の地域を表すラテン語の言葉です。
中世までのヨーロッパでは国際語としてラテン語が使われていました。

楽器:フルート
- 夜になり、水面に月が映し出されている様子
- 水の精が現れて、月の光とたわむれて踊っているよう
- そこにヴァイオリンとオーボエが入り、ブルタバの旋律を表現
- このブルタバの旋律は「朝の訪れ」を表している

楽器:金管楽器、チェロ、コントラバス
- 急斜面を水が激しく落下する様子
- 大きく激しい演奏
- 緊張感がある

楽器:木管楽器、ヴァイオリン
- 再びブルタバが穏やかさを取り戻した様子
- 長調(明るいイメージ)でブルタバのテーマが表現される
 Parník Vyšehrad pod Vyšehradem - ヴィシェフラット - Wikipedia
Parník Vyšehrad pod Vyšehradem - ヴィシェフラット - Wikipedia
楽器:フルート、ピッコロ
- 川が大きく広がっていき、ビシェフラトの丘を通り抜ける
- 堂々とした印象
- ※ビシェフラトの丘はかつて王宮があった場所(↑画像)
プラハやブルタバといえば!

プラハといえば「音楽の街」で「世界で最も美しい街の一つ」と言われますよね。
ぜひ行ってみたいのですが、その中でも特に有名なのが「カレラ橋」と「グラスハープ」です。
カレラ橋とは
カレラ橋は今回のテーマのブルタバ川に掛かる橋なのですが

- プラハで最も古い橋
- 1375年から約60年掛けてつくられた
- 全長約520m、幅10m
- 聖人の像が約30体並ぶ
- 絵描きや大道芸人、露天商いつも賑わう
→ということですごい楽しそうだから行ってみたい!
グラスハープ
「音楽の街プラハ」では、いつも街中で誰かの演奏がされているということですが、その中でも特徴的なのがグラスハープです。
グラスハープは、水の入ったっグラスを指でなぞり、その摩擦で演奏する楽器で、意味は分かりますよね。
と思ったら、演奏を見てみたところ、そんなものじゃありませんでした。
まだの方は↑の動画をぜひご覧ください。
「え、本当にグラスから音でてる?」って思うくらいスゴイですよね!
これを生で、プラハで見てみたいです。